KIYOSHI SHIGEMATSU / MOKUYOBINO KODOMO
Publication 2022.1.25 KADOKAWA BUNKO
重松清「木曜日の子ども」を読了。
直木賞作家としても知られる重松氏は家族物を書かせると天下一品。
これまで触れてきた重松作品「その日のまえに」「流星ワゴン」「ビタミンF」等はいずれも、
「人生の応援歌」とも言える温もりのある作品だったのに対し、
今回手に取った「木曜日の子ども」は家族をテーマにしている点こそ変わらないものの、
これまでのイメージを覆すディープなミステリーは衝撃的で、
作者の深淵をのぞいた気持ちです。
ストーリーをざっくり書くと、
夫のDVに悩まされ離婚しシングルマザーとして中学生の一人息子を育てる女性は、
職場で出会った男性と再婚しとある街で新たな生活を始める。
継父となった男性と息子はぎこちないながらも距離を縮めようと日々を送る。
しかし、ある日隣家で起こる予想だにしない出来事から
話は思いがけない方向へ転がってゆく・・・
わたしは幼い頃、親が喜ぶことが何なのかを察知し立ち居振る舞っていました。
父の狂気と母の溺愛。
両親は愛情を注いで育ててくれましたがそこには強烈なエゴも同居しており、
自我が芽生えると共にそれを皮膚感覚で感じ嫌悪する瞬間もありました。
「木曜日の子ども」は、
そんな幼少期の何とも言えない記憶を呼び起こし、
作中の子ども達の発想も分からないでもない・・・
と、気がつけば自分を重ねていました。
作品は中盤まで圧倒的に面白い。
作者の重松氏も筆が乗って止まらなかったのではないかと。
けれども、終盤は考えに考え時に逡巡し物語を綴った印象があります。
言わば中盤までは直感的に終盤は技巧的に書いた作品なのではないかという考察です。
こう書くと終盤が面白くなかったかのような誤解を与えそうですが、
最後までスリリングで予想を裏切る展開はとても面白い。
けれども、最後まで直感的に書き殴ることが出来たのであれば、
更に面白かったのか収拾がつかなくなってしまっていたのか・・・
どうだったのだろうと勝手な思いを馳せてしまうのです。
直木賞作家を前に勝手な考察を立てているに過ぎませんが、
それ程までに引き込まれる瞬間があった作品で、
秀作であることは言うまでもありません。
重松清「木曜日のこども」 ( 角川文庫 令和4年 1月25日 初版刊行 )







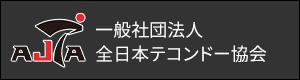


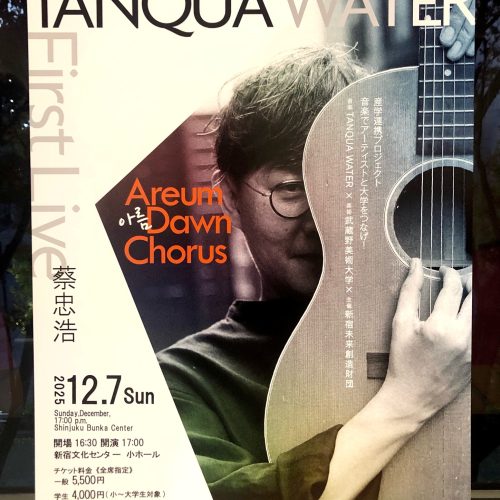



最近のコメント